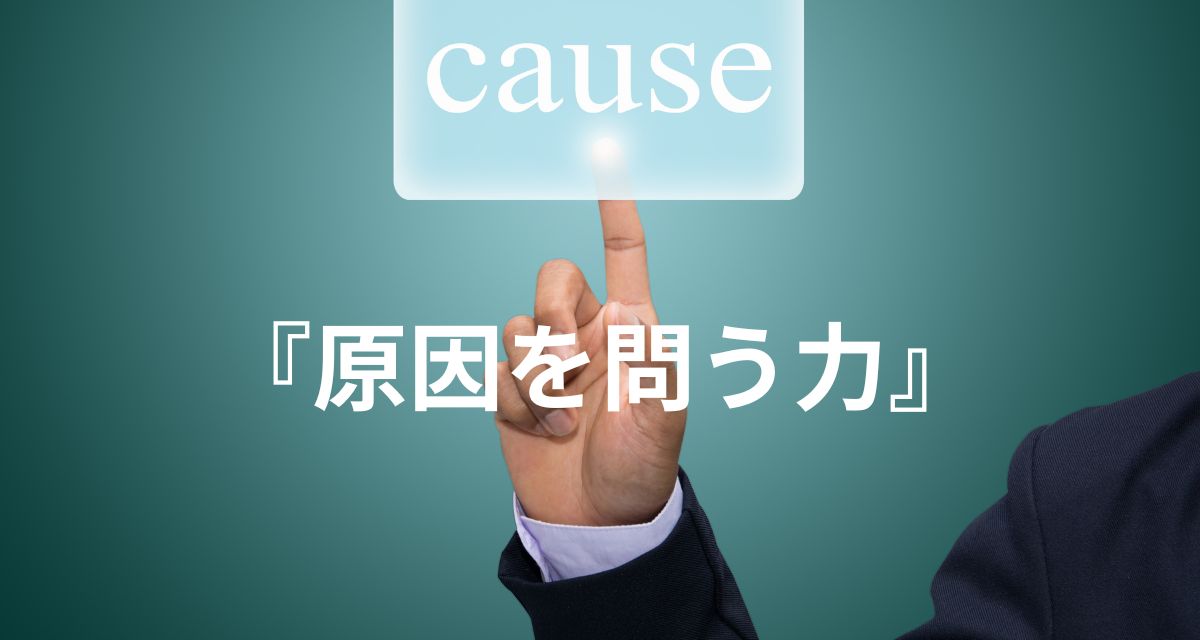収益と利益の最大化を支援する
プロフィット・コーチの小林 剛です!
『結果』を出すなら、『(財務)知識』と『意識』で、PDCA
経営やコンサルティングの現場で「財務分析」という言葉は頻繁に使われます。
損益計算書(P/L)や貸借対照表(B/S)、キャッシュフロー計算書(C/F)などの財務三表を見て、売上・利益・資産・負債・キャッシュの動きをチェックする。
これは“分析”の基本ですが、数字を眺めただけでは、まだ「観察」にすぎません。
本当に大事なのは、
なぜこの数字になったのか?
どうしてこういう変化が起きたのか?
という“問いを立てる力”なのです。
財務分析とは、数字の背景を読み解き、未来の意思決定に活かすための「思考の道具」なのです。
数字は「結果」にすぎない─“見えない原因”に目を向ける

たとえば、ある企業の営業利益率が、前年 8% → 今年 5% に下がっていたとします。
この変化を見て、「利益が落ちた」と嘆くだけでは、何も改善にはつながりません。
数字はあくまでも“結果”であって、その裏には必ず“構造”と“原因”があります。
考えるべき問いは、こうです:
- 原価が上がったのか?(仕入・材料・外注費の上昇)
- 販売単価が下がったのか?(値引きや競争激化)
- 商品構成が変わったのか?(利益率の低い商品が売れた)
- 販売数が減ったのか?(需要減退や競合増加)
- 販管費が増えたのか?(広告費、人件費、間接費など)
こうした原因を探り出してこそ、「では、どう改善するか?」という行動に結びつくのです。
財務分析の本質は、「問いを立てること」

財務諸表とは、経営という“試合のスコアボード”のようなもの。
点差が開いている理由を考えなければ、次の戦略は立てられません。
数字を見て終わりではなく、「問いを立てて深掘りする」ことこそが、真の財務分析です。
数字 → 問い → 原因 → 行動
という思考プロセスを経ることで、数字は“未来を動かす武器”へと変わります。
◆ 実例:営業利益率が落ちた原因をどう掘るか?◆
ここでは、営業利益率が低下した企業の事例をもとに、分析の流れを整理してみましょう。
① 数字の確認
営業利益率が**前年8% → 今年5%**に下落。
② 仮説を立てる
「どのコストが増えた? 収益性の構造が変わった?」
- 原価率が上がっていないか?
- 売れ筋商品の変化はないか?
- 特定部門や顧客層に偏りはないか?
③ データを分解・分析
- 原価率:65% → 72%
→ 仕入単価の上昇、外注比率の増加 - 販管費:ほぼ横ばい
- 売上構成:利益率の低い廉価商品が売上の多くを占めるようになった
④ 原因の特定
- 「原価管理の緩み」
- 「商品構成の変化(ミックスの悪化)」
⑤ 改善策の立案
- 粗利率の高い商品を中心に販売強化
- 価格交渉や原価削減の見直し
- 外注の内製化または業者選定の再検討
このように、「数字を問いに変える」ことで、初めて財務分析は経営改善に直結する力になります。
財務分析は、『未来を変えるためのツール』

財務諸表は過去の結果を表すものですが、その“結果”には必ず“原因”があり、その“原因”は未来を変えるヒントとなります。
数字とは、意思決定の出発点であり、経営改善のシグナルです。
「数字を通じて未来を読み、行動する」
これが、財務分析の本質です。
◆ 経営者・財務担当者が持つべき“3つの視点” ◆
| ❌ よくある落とし穴 | ✅ 本当に必要な視点 |
| 数字を見て安心・不安で終わる | 数字の裏にある「構造と行動」を読み取る |
| 利益率や比率だけで評価を終える | 具体的な要因や内訳まで掘り下げる |
| 財務諸表を「報告資料」として扱う | 「経営判断ツール」として使いこなす |
まとめ:数字の“奥”にこそ経営改善のヒントがある
数字を読むことは大切です。
しかし、もっと大切なのは、数字の「奥」にある“原因”や“構造”を見抜くこと。
数字を「なぜ?」と問い直す力が、
あなたの経営を、数字主導から“意思決定主導”へと導いてくれます。
財務分析とは、単なる“数値の解釈”ではなく、
“未来を創るための問いを立てる思考プロセス”なのです。