
収益と利益の最大化を支援する
プロフィット・コーチの小林 剛です!
『結果』を出すなら、『(財務)知識』と『意識』で、PDCA
中小企業の経営者や財務責任者の皆さん、
『貸借対照表における総資産の大きさ=経営リスクの大きさ』という視点で、自社の財務状態を見たことはありますか?
これは一見すると極端な見方に思えるかもしれませんが、実は非常に本質的な経営分析の視点です。
この記事では、総資産の意味や、規模が大きいことによって生じる経営リスク、
そして「ROA(総資産利益率)」という重要指標を交えて、経営者が持つべき視点を深堀していきます。
総資産とは?

貸借対照表(B/S)における総資産とは、企業が保有するすべての資産、つまり経営のために使っている「モノ・カネ」の合計を指します。
具体的には、現金、売掛金、在庫、設備、不動産などが含まれます。
📌 総資産の式:
総資産 = 負債 + 純資産(自己資本)
資産が多いということは、それだけ多くの「経営資源を抱え、運用している」ということ。
つまり、企業規模の裏返しであり、同時に「経営の重さ」を表しているとも言えます。
なぜ総資産が大きいと経営リスクが高まるのか?
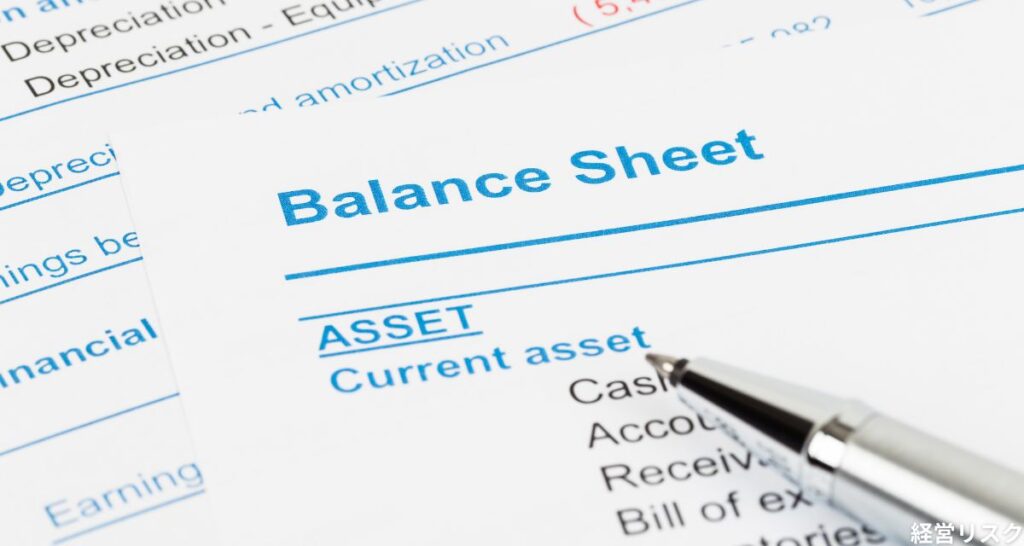
ここで注目したいのが、「資産が大きければ安心」ではないということ。
むしろ、資産が大きいほど管理・運用・回収にコストとリスクがかかるため、企業の柔軟性や安全性を損なうこともあるのです。
| リスクの視点 | 解説 |
| 固定費の重さ | 設備投資で資産が膨らむと、減価償却や維持管理費がかさみます。売上が下がっても支出が固定化されているため、損益分岐点が高くなり、経営の安定性を損ないます。 |
| 借入依存の可能性 | 総資産が大きい企業は、借入で資産を賄っている場合が多く、利息や返済の負担が資金繰りに影響します。 |
| 資産の回転効率 | 資産を持っていても、売上や利益につながっていなければ、それは「眠っている資産」です。回転効率が悪く、収益性も低下します。 |
| 柔軟性の低下 | 巨大な設備や在庫を抱えると、環境変化に対する事業の切り替えや規模縮小が難しくなります。 |
ROAの視点が重要な理由
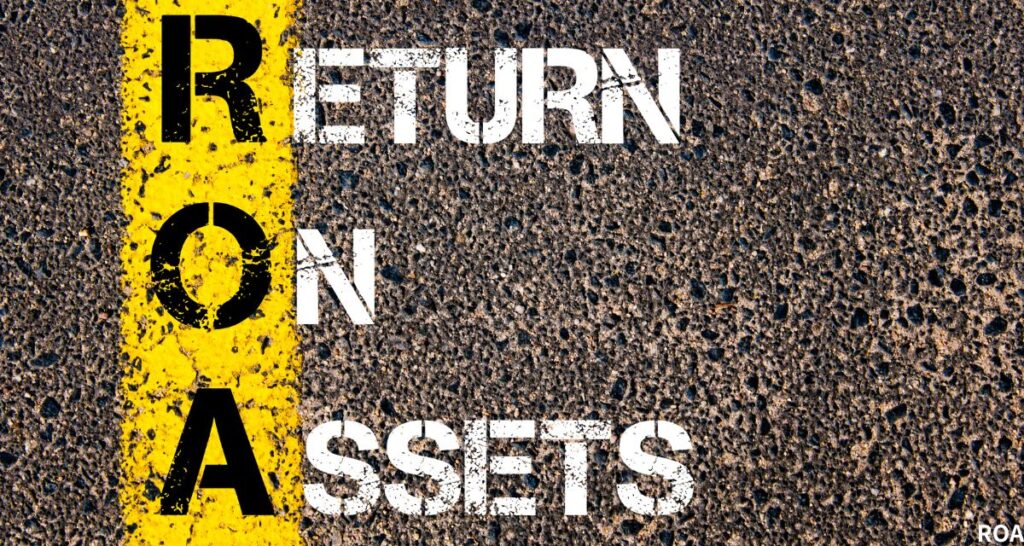
資産が大きいからといって、必ずしも悪いとは限りません。
ポイントは、「その資産を使って、どれだけ利益を出せているか」です。
ここで重要になるのが、ROA(総資産利益率)です。
💡 ROA(総資産利益率)= 経常利益 ÷ 総資産
◆ ROAの目安と経営の判断 ◆
| ROA水準 | 評 価 |
| 5%以上 | 資産を効率よく活用できており、優良企業の水準 |
| 3〜5% | 安定的で一定の経営効率が確保されている |
| 1〜3% | 資産に対して利益が十分ではなく、改善余地あり |
| 1%未満 | 資産が“寝ている”可能性が高く、財務リスク大 |
資産の大きさそのものより、「その資産でいくら稼いでいるか」を重視しましょう。
◆ 小さな総資産の経営には、こんなメリットも ◆
| 項 目 | 内 容 |
| 軽量経営 | 資産をスリムに保つことで、事業モデルの変更や撤退も迅速に行える柔軟性が高まります。 |
| 高い資産回転率 | 少ない資産で多くの売上・利益を出すことで、経営効率が高まり、収益体質が強化されます。 |
| リスク耐性 | 固定費・借入・資金拘束が少ないため、不況時にも黒字維持がしやすく、倒産リスクが低下します。 |
◆ 経営者が意識すべきチェックポイント ◆
| チェック項目 | 視点 |
| 総資産の規模 | なぜこの資産が必要か?過剰ではないか? |
| 資産の回転効率 | 売上高や利益と比べて、資産の動きが鈍くないか? |
| ROAの水準 | 自社のROAは何%か?資産に見合う利益が出ているか? |
| 軽量化の可能性 | 売掛金、在庫、遊休資産など、資金化できるものはないか? |
まとめ : 資産は「持つ」より「活かす」時代へ
企業の貸借対照表を見て、「総資産が多い=安心」と考えるのはもう古い発想です。
これからの時代、資産を抱え込むほど経営は重く、遅く、リスクが高くなります。
🔑 経営の鍵は、「資産をどれだけ効率的に回し、利益を生んでいるか?」
そしてそれを示すのがROAです。
👉 経営者の皆さまへ:「資産は戦力であると同時に、重荷にもなる。」
だからこそ、資産は“持つ”より“活かす”という視点が、いま求められています。

