
収益と利益の最大化を支援する
プロフィット・コーチの小林 剛です!
『結果』を出すなら、『(財務)知識』と『意識』で、PDCA
私の支援先のお客様で、2023年度、2024年度の決算状況を鑑み、役員に対するボーナスを支給することが出来ました。
営業利益の20%を事前確定届出給与制度を使って、12月にクリスマスボーナスとして、支給しました。
近年、注目を集めているのが「事前確定届出給与」を活用した、業績連動型の役員報酬制度です。
今回は、実際にこの制度を導入し、営業利益の20%を役員へ支給したという事例を基に、その詳細やメリット・デメリットについて掘り下げていきましょう。
事前確定届出給与とは?
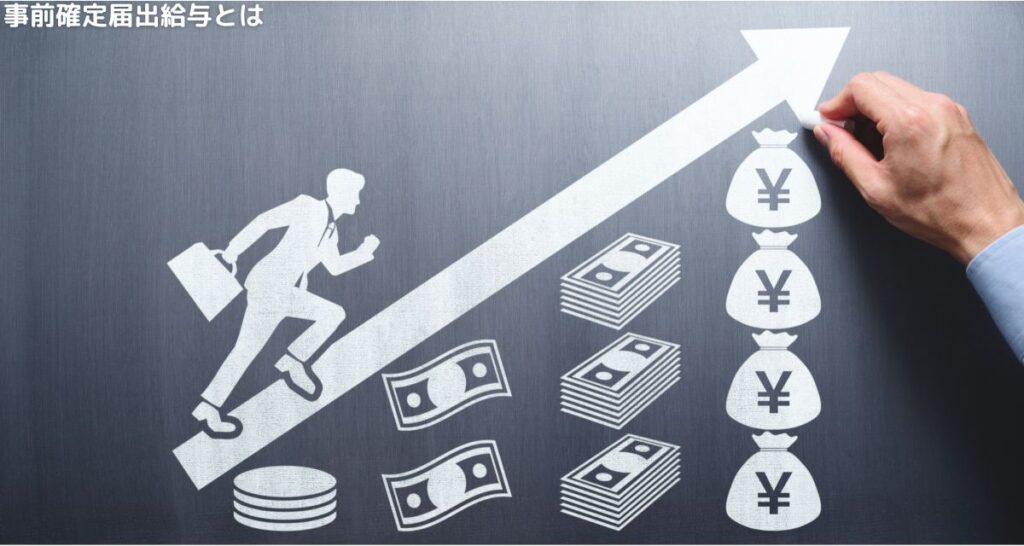
まず、「事前確定届出給与」について簡単にご説明します。
これは、一定の時期までに、支給額や算定方法などを税務署に届け出ることで、損金として認められる役員給与のことです。
通常の役員給与は、毎月定額で支給される必要がありますが、事前確定届出給与を活用することで、業績目標の達成度合いに応じて変動する報酬を役員に支払うことが可能になります。
【事例:営業利益の20%を役員報酬に】
今回ご紹介する企業では、「当期の営業利益の20%を、役員報酬として支給する」という決定をし、事前確定届出を税務署に行いました。
この制度設計の背景には、以下のような目的がありました。
- 業績向上への強いインセンティブ付与:
役員の報酬が直接的に会社の利益に連動することで、より一層の業績向上意欲を引き出す。
- 株主との利益共有:
会社の利益成長を役員と株主が共有することで、一体感を醸成し、企業価値の向上を目指す。
- 透明性の確保:
事前に支給基準を明確にすることで、役員報酬の決定プロセスにおける透明性を高める。
メリットは?

この事例のような業績連動型報酬制度には、以下のようなメリットが考えられます。
- 明確な目標設定:
役員は、自身の報酬額を最大化するために、具体的な営業利益目標の達成に向けて注力するようになります。
- コスト意識の向上:
利益に連動するため、役員は無駄なコストを削減し、収益性を高める意識を持つようになります。
- 優秀な人材の獲得・維持:
魅力的な報酬制度は、優秀な経営人材の獲得や、既存の役員のモチベーション維持に繋がります。
- 株主への説明責任:
業績との連動性が明確であるため、株主に対しても報酬の妥当性を説明しやすくなります。
デメリット・注意点は?
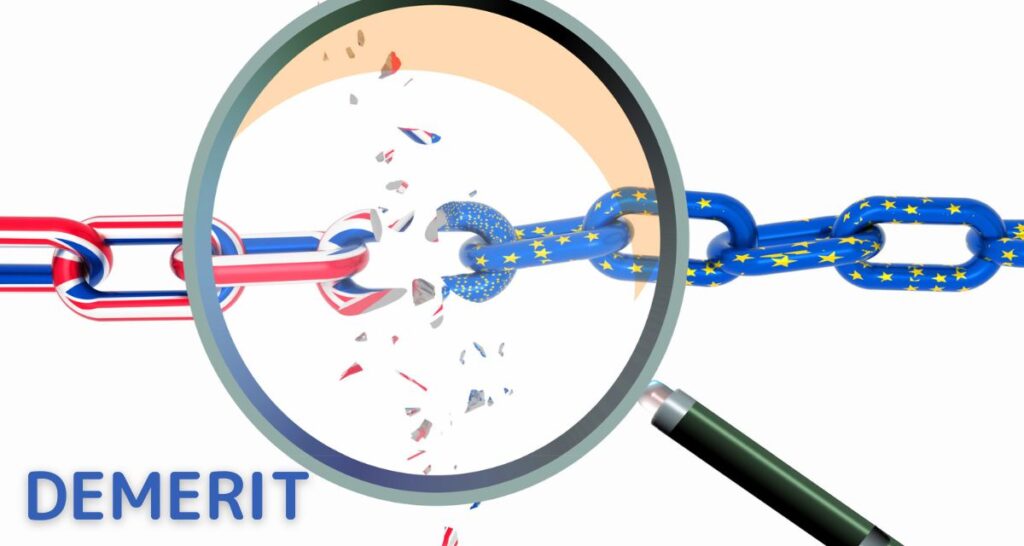
一方で、このような制度設計には、いくつかのデメリットや注意点も存在します。
- 短期的な視点に偏る可能性:
過度に短期的な業績に連動させる場合、長期的な成長戦略が犠牲になる可能性があります。
- 不確実性の影響:
経済状況の変動など、役員の努力だけではコントロールできない要因によって、報酬が大きく変動する可能性があります。
- 制度設計の複雑さ:
適切な連動指標の選定や、目標設定の難しさなど、制度設計には専門的な知識が求められます。
- 税務上の要件:
事前確定届出給与として認められるためには、厳格な要件を満たす必要があり、不備があると損金算入が認められない可能性があります。
まとめ
「営業利益の20%を役員報酬とする」という事例は、事前確定届出給与を効果的に活用した、大胆かつ革新的な報酬制度と言えるでしょう。
業績向上への強いインセンティブを付与する一方で、制度設計や外部環境の変化への対応など、慎重な検討も必要となります。
今後、企業の持続的な成長のためには、画一的な役員報酬制度ではなく、各企業の戦略や状況に合わせた柔軟な設計がますます重要になってくるのではないでしょうか。
今回の事例が、皆様の役員報酬制度設計の一助となれば幸いです。

